近年、副業を始めるサラリーマンが急増しています。しかし「副業をすると税金が高くなるのでは?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。実は、正しい知識を身につければ、副業は「収入を増やす」だけでなく「節税」にもつながります。本記事では、「サラリーマン」「副業」「節税」という3つのテーマを軸に、誰でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。
サラリーマンが副業をする背景と税金の基本
副業解禁の流れと働き方の変化
副業を認める企業が増えている今、サラリーマンにとって働き方の選択肢は確実に広がっています。その理由は、政府の「働き方改革」によって、長時間労働を減らし、柔軟なキャリア形成を推進する流れが強まっているからです。例えば、以前は副業禁止規定が当たり前でしたが、厚生労働省がモデル就業規則を改定したことで、副業解禁を進める企業が増加しました。その結果、会社に依存せずスキルを磨いたり、収入源を複数持つことが現実的になっています。つまり、副業解禁の動きは、サラリーマンに新しい働き方と可能性をもたらしているのです。
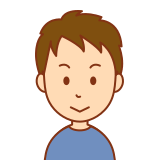
政府も副業を推進しているんだね!!
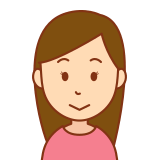
複数の収入源を持てるのは魅力的ね
副業収入と所得税の関係
副業で得た収入は必ず税金と関わるため、その仕組みを理解しておくことが重要です。なぜなら、副業収入は「雑所得」または「事業所得」に分類され、課税対象となるからです。例えば、ライター業やネット販売で継続的に利益が出る場合は事業所得となり、経費計上や青色申告特別控除が可能になります。一方、単発のアルバイトやフリマアプリでの収益は雑所得とみなされ、控除の幅は狭くなります。この違いを知らないと不要な税負担や申告漏れにつながりかねません。結論として、副業を始めるサラリーマンは、収入の種類ごとに課税ルールを把握し、正しく申告することが大切なのです。
事業所得とは?
継続性があり、事業として成立している所得であり、節税メリットが大きくなります。
雑所得とは?
小規模・一時的であって事業とまではいえない所得であり、控除や経費の選択の幅が狭くなります。
サラリーマンの副業で活用できる節税方法
必要経費を計上する
副業で得た収入を正しく節税するためには、必要経費を計上することが最も基本的で効果的です。なぜなら、収入から経費を差し引いた金額に対して税金がかかるため、経費が多ければ課税対象額が小さくなるからです。例えば、副業用に購入したパソコンやソフト代、打ち合わせに使うカフェ代、ネット通信費の一部などは経費として認められる可能性があります。こうした支出を領収書や明細とともに記録しておけば、確定申告の際に根拠を示すことができます。つまり、副業に関連する支出をこまめに整理して経費に計上することが、サラリーマンにとって最も手軽で効果的な節税の第一歩となるのです。

青色申告で控除を受ける
副業を本格的に行うサラリーマンにとって、青色申告は大きな節税手段になります。なぜなら、事業所得として認められれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるからです。例えば、副業としてライティングやデザイン業を継続的に行い、帳簿を正しくつけていれば、この控除を適用でき、所得税の負担を大幅に減らすことが可能です。また、家族に給与を支払う「青色事業専従者給与」の仕組みを利用すれば、さらに節税の幅を広げられます。結論として、サラリーマンであっても副業が事業と認められるなら、青色申告を活用することは大きな節税メリットを生むのです。
青色申告:税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記もしくは簡易簿記に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告することである。青色申告ではない申告方法は白色申告と呼ばれる。

小規模企業共済やiDeCoで将来に備えながら節税できる
将来に備えつつ節税したいサラリーマン副業者におすすめなのが、小規模企業共済やiDeCoです。なぜなら、これらは掛金が全額所得控除となり、税金を抑えながら老後資金を準備できる仕組みだからです。例えば、月2万円をiDeCoに拠出すれば、その金額分だけ課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽くなります。また、小規模企業共済は廃業や退職時に受け取れる退職金のような性質を持ち、将来のセーフティネットとしても機能します。つまり、これらの制度を利用すれば「節税」と「資産形成」を同時に実現でき、副業サラリーマンにとって一石二鳥の選択肢となるのです。

副業サラリーマンが気をつけたい注意点
会社にバレない方法はある?
副業をしていることを会社に知られたくないサラリーマンは多いですが、完全に隠すのは難しいものの、工夫次第でリスクを下げることは可能です。なぜなら、副業が会社に知られる最大の原因は「住民税の通知」であり、ここをコントロールできればバレる確率を減らせるからです。例えば、確定申告の際に住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」にすれば、会社の給与から天引きされず、会社へ副業収入が通知されにくくなります。また、副業先の給与を源泉徴収されるままにしておくと会社に情報が届きやすいため注意が必要です。結論として、副業を完全に隠す保証はありませんが、住民税の納付方法を工夫することで会社に伝わる可能性を低くすることができます。
確定申告を怠るとどうなる?
副業で収入を得たサラリーマンが確定申告を怠ると、思わぬペナルティを受ける可能性が高まります。なぜなら、税務署は副業先から提出される支払調書やマイナンバー制度を通じて収入を把握しており、申告漏れはすぐに発覚するからです。例えば、20万円以上の副業収入を申告せずに放置していると、「無申告加算税」や「延滞税」といった追徴課税が課され、余計な支払いが発生します。さらに悪質と判断されれば「重加算税」として本来の税額の最大40%が上乗せされるケースもあります。結論として、副業収入が少額であっても正しく申告することが、余計なリスクを回避し安心して副業を続けるための必須条件なのです。
Q&Aセクション
Q1: サラリーマンの副業収入はいくらから確定申告が必要ですか?
A1: 年20万円を超える副業収入がある場合は、原則として確定申告が必要です。
Q2: 副業で使ったスマホ代や家賃は節税できますか?
A2: 副業に使った割合を合理的に計算すれば、通信費や家賃の一部を経費として計上できます。
Q3: 副業がバレないように節税する方法はありますか?
A3: 住民税を普通徴収に変更するのが一般的です。ただし、100%防げるわけではありません。
Q4: サラリーマンでも青色申告はできますか?
A4: 事業として継続性・独立性がある副業なら、サラリーマンでも青色申告を利用できます。
Q5: 節税だけを目的に副業をするのはアリですか?
A5: 本来の目的は「収入を増やす」ことです。節税は結果的なメリットとして捉えるのが望ましいでしょう。
まとめ
近年、副業を始めるサラリーマンが増えていますが、正しい知識を持つことで「収入アップ」と同時に「節税」も実現できます。本記事では、副業解禁の背景や副業収入と税金の関係、さらに必要経費の計上・青色申告・iDeCoや小規模企業共済といった実践的な節税方法を解説しました。重要なのは、税金の仕組みを理解し、確定申告を正しく行うことです。これにより、無駄な税負担を減らし、安心して副業を続けられます。
次に取るべきステップとしては、まず副業の収入と支出をしっかり記録し、どの節税制度が自分に合うかを確認することです。特に初心者は、領収書を残す習慣や住民税の納付方法の確認から始めるのがおすすめです。
「サラリーマンの副業でできる節税術|初心者でも今日から実践できる方法」を参考に、一歩ずつ行動していけば、収入を増やしながら将来に備える賢いマネープランを築くことができるでしょう。
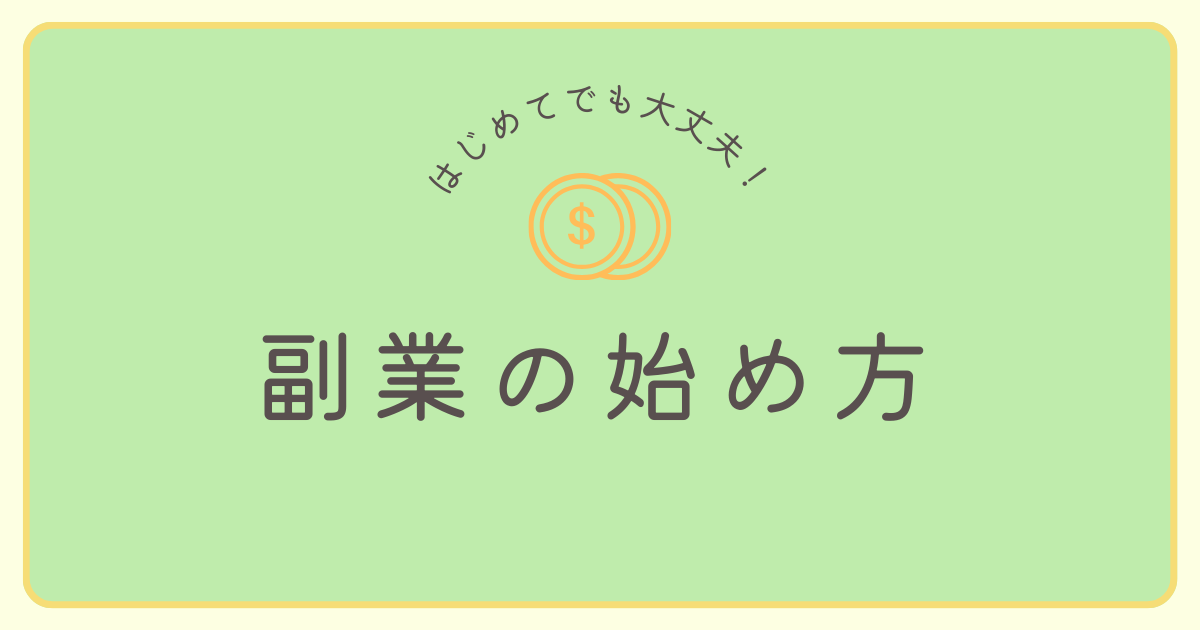
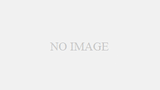
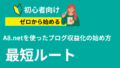
コメント